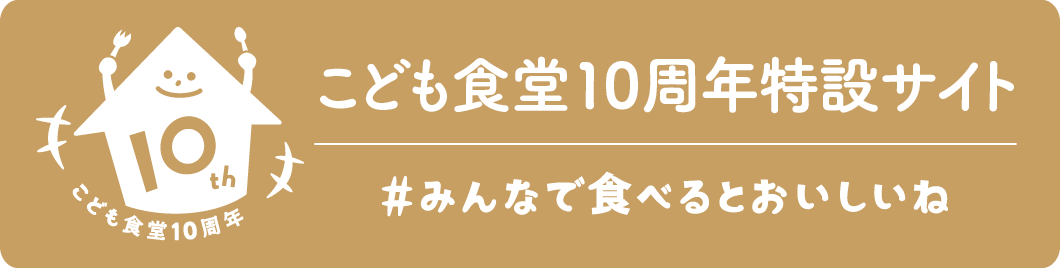いざというときも日常も。助け合える関係をつくるこども食堂
「公開ワークショップ 話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」in 大分 開催レポート
全国47都道府県で実施している「公開ワークショップ 話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」。22回目の開催地は大分県。2024年11月15日、スタジオ・ナ・コスタで開催されました。主催は、おおいたこども食堂ネットワーク(社会福祉法人大分県社会福祉協議会)です。現在の大分県のこども食堂の数は約153。子どもから高齢者まで、地域のみんなの居場所になっているところが多いようです。今回のワークショップには、こども食堂の運営者や社協、行政関係者など約46名が参加しました。それでは、今回も登壇者のみなさまが実際に経験したエピソードをもとに語られた、「食べるだけじゃない」こども食堂の魅力をご紹介します。
地域に緩やかなつながりをつくる、こども食堂
本ツアーで実施するワークショップでは、こども食堂の運営者のみなさんに、1人ずつ 「やっていてよかったと感じるエピソード」「忘れられないエピソード」を伺っています。どのエピソードも、ハッとさせられたり、心温まったりするものばかり。エピソードの一端をご紹介します。
地域のみんなで見守り合い、声をかけ合う温かさ
NPO法人しげまさ子ども食堂-げんき広場-(豊後大野市)首藤文江さん:
2016年にこども食堂を始めて9年目になりますが、今でも覚えている立ち上げ当初の印象的な出来事があります。こども食堂を始めたきっかけの1つに、「子どもたちに気軽に『おかえり』や『いってらっしゃい』を言えなくなった」という地域の人の声を聞いたことがありました。そのため、立ち上げの際には、賛同してくれた方々と、どうしたら安心して声をかけられる関係がつくれるか、何度も話し合いを重ねました。そんななか、とあるスタッフの家の前を車で通ったときのことです。それまでは、お互いを認識しても会釈をするくらいでしたが、彼が「おーっ!」と私に向かって満面の笑顔で手を挙げてくれたのです。立ち上げの大変さや不安な気持ちが一気に軽くなり、通り過ぎた後も感動してじんわりと涙が出てきました。このような地域のつながりを子どもたちにも広げていきたいと、心からそう思いました。今では、子どもたちはもちろん、スタッフや地域の方々も、すれ違うときにはお互いに手を挙げて挨拶をしてくれます。こども食堂を通じて、地域で「知っているこども」「知っているおとな」に声をかけ合える関係性ができたことを、とても嬉しく感じています。
お祭りで出番をつくる。任せて育む、子どもの得意
集いの場”くるみ”(別府市)原田康子さん:
私たちのこども食堂で大切にしているのは、子ども一人ひとりの強みを見つけて、それを育てること。その舞台として活用しているのが、地域のお祭りです。こども食堂の中高生ボランティアが中心になって企画を進め、今年は焼き芋販売を行いました。焼き芋を入れる袋を新聞紙で作る際には、小学生の男の子が大活躍。その子は普段は人と接するのが苦手なのですが、折り紙は得意。みんなの先生になってくれるようお願いしたところ、イキイキとした表情でみんなに折り紙を教えてくれました。お祭りで意外な一面を見せてくれたのは、中学生の女の子。いつもは物静かなのに、「おいしいお芋だよー!」と、今までに聞いたことのない大きな声で焼き芋をアピールしてくれました。過去には、いつもおとなしい子が飛び込みで地域の団体に混じって、ひょっとこ踊りを踊ったこともあります。その子はその後、団体にスカウトされて、一緒にいろいろなイベントを回ったそうです。こども食堂をきっかけに、子どもたちの新しい才能が花開いていくことをとても嬉しく思っています。
誰も取り残さない。親も子も、一緒に関係性を築く大切さ
みんなの食堂(津久見市)高橋和希さん:
2017年に津久見市が台風による甚大な被害を受けた際、ボランティアに携わったことがこども食堂を立ち上げたきっかけです。復旧活動を通じて、孤立している高齢者や支援が必要な家庭の存在に気づいたのです。神父をしている教会で災害ボランティアセンターを立ち上げたのですが、そこを閉じる際に、このままでは終われないと、こども食堂を始めました。現在は、こちらから声をかけた20家庭ぐらいが利用をしています。印象的だったのは、少し障害がある子どものいる、とある家庭です。子どもが必要なサポートを受けられていない状態だったので、様子を見ながら少しずつ声をかけ、こども食堂に来てもらえるようになりました。その後、医療関係のスタッフと相談にのっているうちに、お父さんと関係性を築けるように。そんなとき、その子が描いた絵が歯科衛生コンクールで優勝したのです。真っ白な歯が描かれたその絵は、その子の純粋な心が現れているようでした。お父さんの嬉しそうな様子も心に残っています。これからも、子どもだけでなく、親のことも一緒に見守っていきたいと思います。
一度も休まず150回。多様な仲間と目指す共生社会
とんとんとん食堂(佐伯市)山内勇人さん:
こども食堂を始めたきっかけは、東日本大震災。ボランティアに行って感じたのは、誰一人必要のない人はいないということです。誰もが孤立せずに、生きがいを持って暮らせる地域をつくりたいと思いました。その後、2015年に認知症カフェを始め、2018年に一般社団法人化し、こども食堂を開くようになりました。子どもも、認知症の人も、障がいのある人もみんな一緒に、ごちゃまぜでやる。それが私たちが大切にしていることです。一番大変だったのはコロナ禍。「不要不急の外出を控えるように」と言われ、理事会さえも開くことが難しくなってしまいました。でもそのことで、自分たちはなんのために、誰のためにやっているのか、改めて考えるきっかけにもなりました。コロナ禍も休まず続けてきたのは、「自分の居場所はここしかない」と言ってくださる方が大勢いたから。ずっと残ってくれているスタッフの多くは、障がいのある方たちです。3人で100人分のカレーを作ったこともありました。コロナ禍を経て感じるのは、仲間や続けることの大切さ。自分自身がこの活動に支えられていることを感じています。
お互いの活動をヒントに考える、これからのこども食堂
登壇者のお話を聞いた後は、会場のみなさんと登壇者との「共感・質問タイム」。こども食堂運営者からの、子どもたちに人気のイベントや、子どもたちに来てもらうにはどうしたら良いか、といった質問に、登壇者のみなさんが丁寧に答えてくださいました。また、「みなさんはどんな場所でこども食堂を開いていますか?」という質問では、急遽、会場のみなさんへアンケート。公民館やお寺の他、自宅や空き家になっている実家、管理と引き換えに場所を無償提供してもらっているなど、さまざまな場所ややり方が共有されました。
終了後のアンケートでは、以下のような意見が寄せられました。
――こども食堂を継続していく苦労を分かち合うことができ、勇気をもらえた。
――「私も何かしたい」と思うきっかけになった。
――コロナ禍から弁当配布になっているが、みんなで一緒にごはんを食べる良さを改めて感じた。
――ほかのこども食堂のやり方を聞くことができて参考になった。うちでも子どもたちにいろいろやってもらおうと思った。
――子どもたちの成長の話に感動した。
こども食堂を体験しよう!
今回も、こども食堂を運営される方の熱い思いが伝わるお話ばかりでした。特に今回は災害をきっかけにこども食堂を始めた方が多く、防災の視点からも改めてこども食堂の重要性を感じる回でした。レポートを読んでくださった方も、「食べるだけじゃない」を体験しに、お近くのこども食堂に参加してみてはいかがでしょうか。
大分県でこども食堂の活動に取り組まれているみなさん、ワークショップへのご協力を誠にありがとうございました。
【開催概要】
「こども食堂公開ワークショップ 話そう!広めよう!~食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」in 大分
開催日:2024年11月15日(金)13:30-16:00
開催場所:スタジオ・ナ・コスタ
主催: おおいたこども食堂ネットワーク(社会福祉法人大分県社会福祉協議会)
共催:全国こども食堂支援センター・むすびえ
登壇者:首藤文江(NPO法人しげまさ子ども食堂-げんき広場-/豊後大野市)、原田康子(集いの場”くるみ”/別府市)、山内勇人(とんとんとん食堂/佐伯市)、高橋和希(みんなの食堂/津久見市)※こども食堂名五十音順
ファシリテーター:山縣郁子(全国こども食堂支援センター・むすびえ)