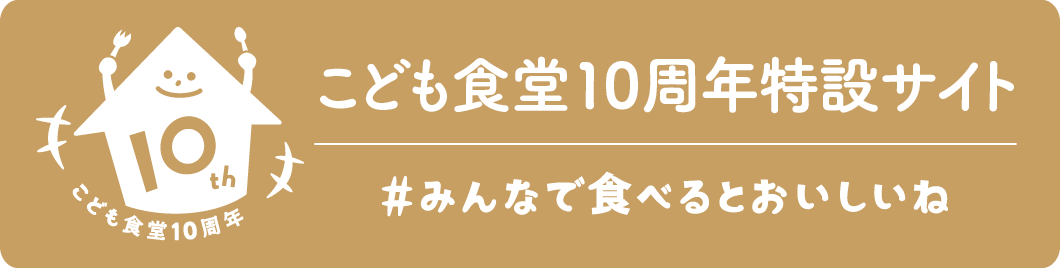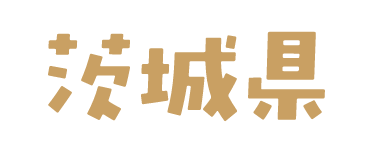子どもたちの未来を照らす、こども食堂の挑戦
「公開ワークショップ 話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」in 茨城 開催レポート
全国47都道府県で実施している『公開ワークショップ 話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること』、21回目の開催地は茨城県。2024年11月11日、ザ・ヒロサワ・シティ会館分館1回集会室8号にて開催されました。
茨城県内には227カ所のこども食堂があり、新規開設も増加傾向にありますが、その広がりには地域差があります。今回、こども食堂で起きている変化のエピソードを共有することで、地域の住民や自治会、行政、企業などからこども食堂への連携を促したいという想いがありました。また、こども食堂の設立、運営まではいかなくとも何かしらの形でかかわりたいと思う人が、多様な参加の形があることを知り、一歩踏み出すきっかけになればとの思いからワークショップを開催しました。
登壇者のみなさまには、実際にこども食堂で出会った人たちとの印象深いエピソードを語っていただきながら、こども食堂の価値について考えました。
学びとつながりを生む場所、 それがこども食堂
本ツアーで実施するワークショップでは、こども食堂の運営者のみなさまに、1人ずつ「活動して印象に残っているエピソード」を伺います。どのエピソードも、気づきがあったり、心が温まったりするものばかり。そのうちいくつかを抜粋してご紹介します。
食の体験が生む子どもの成長
ami seed(阿見町) 林久美子さん:
ami seedは阿見町を中心に家庭で余った食料を配布するフードパントリーやこども食堂「おにぎり食堂」、無料塾、地域の居場所づくりなどの活動をしています。おにぎり食堂を始めたのは、無料塾に来る子どもたちの中に、食に困っている子どもたちがいることを知ったのがきっかけでした。
おにぎり食堂では子どもたちにも実際に料理を作ってもらっています。あるとき、小学校中学年くらいの男の子が来てくれたことがありました。ちょうど梅干を使う料理を作っていたので和える手伝いをしてもらいました。ところが、いざ食べるときになって「梅干は嫌いだから食べない」と言います。「自分で和えたんだから食べてごらん」と促すこと数回。しぶしぶ口にするとパッと目が輝きました。あのときの顔は忘れられません。食べられないと思っていたものを、克服できたり、美味しく食べる工夫を学んだり、子どもにとっての気づきがあったのが嬉しかったです。
実は、私の育った家庭では母親が肉を使った料理が好きではなく、私自身ハンバーグを家で作れることを知らずに育ちました。中学の調理実習で「ハンバーグなんてお家でお母さんが作っているから珍しくないでしょう」という教師の言葉に驚いたことを今でも覚えています。ところが、おにぎり食堂でハンバーグを作ったとき、たくさんの子どもたちから「家で作れるの?」と聞かれたんです。今の子どもたちに体験が不足していると感じました。
さまざまな体験は子どもにとって大切なものだと思います。私は中学校の体験を通して調理師になろうと決意しました。こども食堂が食事を提供するだけでなく、今まで自分ができなかったことができるようになったり、将来の夢を見つけたり、いろいろな可能性に繋がっていく場になればいいなと思っています。
高校生ボランティアが見つけた自分の未来
土浦わかもののまちプロジェクト(土浦市) 酒井慶太さん:
2023年11月に土浦わかもののまちプロジェクトを立ち上げました。人口減少が進む中、土浦で若い人にもっと楽しい思い出を作ってもらいたい、若い人の意見が反映されるまちづくりをしたい、という想いで活動をしています。
私は普段教師の仕事をしているので、子どもたちに「教えて育てる」ことを本業にしています。しかしいつも感じているのは、子どもたちが社会のことをあまりにも知らないということです。子どもたちには、教えてもらったことを学ぶだけでなく、自ら社会と関わることで、広く今の社会を知り、経験を通して成長してほしい、そんな想いからこども食堂の運営をしています。
当団体で運営する「放課後こども食堂」は平日の夕方に開催していますが、食事の提供も遊びに来た小学生の学習支援を行うのもすべて高校生がボランティアで行っています。子どもたちに勉強を教える高校生の中に、学校の教室に入ることができない高校三年生の女の子がいました。1年前は積極的に参加する様子ではなかったのですが、今では子どもたちとのかかわり方や勉強の教え方も自分で考えて工夫し、中学生の進路相談まで受けるように。それからは主体的に動くようになり、慈善活動の提案などもしてくれるようになりました。自分自身の進路を考える時期には、「学校の先生になりたい」と教育学部を志望。教師をしながらまちづくり活動をしている私の姿を見てくれていたようで、子どもは大人の姿を見て考え、成長していくのだと実感しました。
学校の教育はかかわれる人が限られていますが、本来子どもは地域でいろいろな大人とかかわりながら成長していくものだと思います。こども食堂には子どもやその保護者、高齢者など幅広い世代が集います。たくさんの人とコミュニケーションをとりながら、失敗も含めた学びを経験できる場であってほしいと思います。
変わらなかった子どもが教えてくれたこと
認定NPO法人NGO未来の子どもネットワーク(龍ケ崎市) 笠井広子さん:
未来の子どもネットワークは、困難をかかえた子どもたちに特化したこども食堂で、11年前に設立しました。現在の登録者数は130~150人ほど。毎週月曜日から木曜日までの夕方以降食事の提供と学習支援活動を行っています。
これまでたくさんの子どもたちの変化を見てきましたが、特に印象に残っているのは、実は変化のなかった子です。その女の子はこども食堂に小学5年生のときから来ていました。おもにトラブルを抱えたときだけ顔を出す子で、進路を考えなくてはいけない中学2年生ころが一番荒れていたように思います。あるとき、行方をくらましてしまった彼女を警察と一緒に一日中探しまわったことがありました。やっと見つけたときの彼女は赤ちゃんのように泣いていて、着ていた白いトレーナーも彼女の血で染まっていました。赤色灯を光らせたパトカーが周りを囲むその赤々とした光景が今でも目に焼き付いています。実はこのとき、本人から警察に「笠井さんになら居場所を教えていい」と連絡があったそうです。こども食堂が彼女にとって受け入れてもらえる最後の居場所だったのではないかと思っています。行政と民間には役割があると思いますが、行政の手からこぼれ落ちていく子どもを、こども食堂で掬っていきたいと思っています。
この女の子は、今では17歳になっています。最近は顔を出さなくなりましたが、こんなに密にかかわって、こんなに大人がそばにいたのに、変化がなかったのは初めてでした。長く子どもに接していると、いつしか慣れてしまって「この子はこうに違いない」と自分の見方で子どもを見てしまう傾向があります。彼女は慣れないことの大切さを教えてくれたような気がしています。
こども未来へのタネを蒔く場所
登壇者から印象に残っている変化のエピソードを伺った後は、会場のみなさんに気になったエピソードや意見を伺う時間を設けました。また、こども食堂の価値についても話し合いました。会場のみなさんの意見から一部をご紹介します。
――こども食堂が手作りすることを教える場だというのが目からウロコでした。
――先生の教えず育てるというコミュニケーションの手法がすごいな、と思った。子どもたちにやらせていると、大人はアドバイスしたくなってしまいそう。
――不登校の子が学校には行けなくてもこども食堂には行けるのはなぜだろうと思った。
――こども食堂の手伝いをしたいと思ってもなかなか踏み込めない方もいると思う。もっと気軽に参加できたらいいと思う。
また、「長く続ける秘訣を聞きたい」という会場の声に対し、登壇者からは「協力してくれる人がいることに感謝し続けること」「皆がやりたいことを毎年見直しながらやる」「ボランティア仲間をニックネームで呼び合うなど楽しみながらやることでスタッフの居場所にもなっている」という返答がありました。
こども食堂で育もう!
こども食堂の在り方は、訪れる人や地域によってそれぞれ違いますが、新しい学びやつながりを育んでくれる場所になっているようです。ワークショップでは、こども食堂という場がどんな価値を生んでいるのかを見つめ直す人たちの熱い想いを感じることができました。このレポートを読んでくださった方も、「食べるだけじゃない」を体験しに、ぜひお近くのこども食堂に足を運んでみてくださいね。
茨城県でこども食堂の運営に尽力されているみなさん、ワークショップへのご協力を誠にありがとうございました!
【開催概要】
「公開ワークショップ 話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」in 茨城
開催日:2024年11月11日(日)13:30-16:00
開催場所:ザ・ヒロサワ・シティ会館 分館1階集会室8号(茨木県水戸市)
主催:認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会、 全国こども食堂支援センター・むすびえ
登壇者:林久美子(ami seed/阿見町)、笠井広子(認定NPO法人NGO未来の子どもネットワーク/龍ケ崎市)、日向寺恵美(鹿嶋市食育クラブわかば/鹿嶋市)、酒井慶太(土浦わかもののまちプロジェクト/土浦市)、滝本可南(ハレとケ/坂東市)※団体名五十音順ファシリテーター:久米麻子(全国こども食堂支援センター・むすびえ)