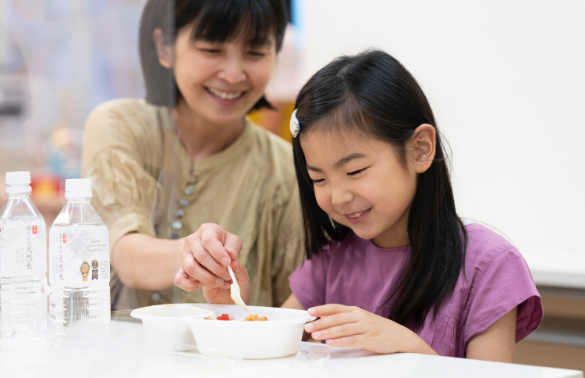地域に根付き、地域で育つ、
地域に開かれたコミュニティ

東京都大田区で「気まぐれ八百屋だんだん」を営んでいた近藤博子さんが、2012年8月に「だんだんこども食堂」を始めました。今では全国に約6000カ所あるこども食堂の先駆けで「こども食堂」名づけの親とも言われています。目の前で起こっている課題を解決したいと一歩踏み出した近藤さんと、そこに集うボランティアの方々にお話をうかがいました。
お話をうかがった方

近藤 博子さん
島根県生まれ。2012年8月より「だんだんワンコインこども食堂」をスタート。気まぐれ八百屋だんだん店主(東京都大田区)。「だんだん」の地域活動が認められ、2019年4月農林水産省第3回食育活動表彰農林水産大臣賞受賞。歯科衛生士。

眞鍋 太隆さん 21歳
小学4年生の頃母親から紹介され、「だんだんワンコインこども食堂」の前身である、喫茶寺子屋へ通い始める。親の転勤でしばらく離れていたが、中学3年生で戻ってくると、近藤さんからボランティアに誘われ参加し始める。福祉分野の勉強をしながら就職活動中。

高良 昌辰さん 22歳
高校の同級生である眞鍋さんに誘われ、「だんだん」を訪問。当時は友達と学校以外で活動をする時間が珍しく、ワクワクしながら「だんだん」へ通った。現在、週1回のこども食堂の献立決めや下準備に関わっている。お土産のパッキングを率先して担当。

折原 聖太さん 21歳
高校3年生の受験が終わった頃、同級生である眞鍋さんから誘われて「だんだん」へ。1日ボランティアとして関わって以来、子どもや地域の人の温かみを感じ、その後の継続を決める。現在は「だんだん寺子屋 お金の勉強会」を中心に参加。
■まずは、温かいごはんと具沢山の味噌汁を!
今年で10年目を迎える「だんだんワンコインこども食堂」は、有機野菜販売の「八百屋だんだん」からスタートしました。八百屋は次第に買い物客が集う場となり、地域の「こんなことできない?」に応えているうちに、毎日イベント・講座が開催されるようになってきました。
2010年、そんな街のよろず相談所のような「八百屋だんだん」で、近藤さんは近隣の小学校副校長から驚くべき話を聞きました。「給食以外の食事をバナナ1本で過ごしている一年生がいる」というのです。ひとり親の母親が病気で食事が作れないと知り、「お隣さんは何をしているんだろう?」「気づいていないの?」と、近隣の人が見過ごしていることにショックを受けました。そんな希薄な社会になってしまったのか――。
「地域の人が手伝えることは何だろう?」
 こども食堂スタート時を振り返る近藤さん。
こども食堂スタート時を振り返る近藤さん。
八百屋はたまたま居酒屋の居抜きだったため、修理したら食卓ができる。温かいごはんと具沢山の味噌汁だけでも食べられたらいいのではないか。そんなアイデアを副校長に伝えると、期待をかける返事をもらい、近藤さんは翌日仲間に相談しました。しかし、地域の仲間は本業を終えてから時間があるときに集まるメンバー。今のようにこども食堂のロールモデルがあるわけではなく、「誰がつくる?」「お金はどうする?」「どうやって子どもたちに伝える?」と一年以上話し合っていました。そうしている内に、バナナ1本で過ごしていた子どもは児童養護施設へ。近藤さんは何もできなかった悔しさを胸に「まず、私がカレー作っちゃうから、みんなは仕事終わったら手伝いに来てくれればいいよ」と、こども食堂をスタートする覚悟を決めました。
■大人「公認」の秘密基地にワクワク
現在ボランティアでこども食堂に関わっている眞鍋さんは、今も続く子どもたちの学習支援の場「だんだん寺子屋」へ小学4年生の頃やってきました。母親の勧めで来たところ、やんちゃな眞鍋さんを見守る近藤さんの視線に厳しさを感じたと言います。しかし、帰り際にみかんをポンッと渡され「なんだ優しい人だ」と一変。以来、一気に入り浸るようになりました。当時の「だんだん寺子屋」はコタツがあり、柱に登ったりぶら下がったり、タイル床にチョークで絵を描いたりできたそうで、都内で普段はできない遊びができる、秘密基地のような場所でした。眞鍋さんが一番覚えているのは、七輪で焼きリンゴ作りにチャレンジしたものの、思うようにはできなかったこと。寺子屋とこども食堂の境もなく、地域の多様な大人と会話しながら多くの子どもたちと関わった、小学生時代の豊かな思い出がよみがえります。
 思いやりのある人柄があふれる眞鍋さん。
思いやりのある人柄があふれる眞鍋さん。
その後、中学生になってからは親の都合で東京から離れていましたが、中学3年生で再び東京へ。帰京後「だんだん」の状況が気になり再訪したところ、近藤さんからボランティアに誘われました。「小学生の頃からお客さんが全然来ていなかったので、つぶれてるんじゃないかと心配で見に行ったんです」と、照れくさそうに優しさをのぞかせます。元々年下の子どもたちから慕われていた眞鍋さんは、多くの子どもと出会い、こども食堂での活動を楽しんできました。その後も子どもが好きそうな友達を連れてきては、共にボランティアとして関わり、時には近藤さんの聞き役になることもあるそうです。
そんな眞鍋さんがボランティアに誘った高校の同級生の一人が高良さんです。家でも学校でもない「だんだん」というサードプレイスで飾り気なくコミュニケーションを取れるのが楽しく、社会人になった今も週1回のボランティアを続けています。こども食堂の献立を考えたり、下準備を手伝ったりしながらお土産のパッキングまで担当します。妹が二人いるため年下の子どもとのコミュニケーションは得意。相手を気遣い過ぎない素直な会話や損得を考えない関係が心地よいと言います。
眞鍋さんが誘ったもう一人のボランティアである折原さんは、「だんだん」を第二の家みたいだと言います。高校生の頃、眞鍋さんに連れられて1日ボランティアをしたところ、子どもたちや地域の人の温かみを感じ、その後の継続を決めました。「最近は、コロナの影響でテイクアウト弁当になっているので、食堂でのボランティアは減っていますが、ここに来ると近藤さんや(眞鍋)太隆たちと会えるし、子どもたちもたくさんいて温かい雰囲気が心地いいんです」
 左:こども食堂では、自分とは違うタイプの子とも話す機会があり面白いと、高良さん。
左:こども食堂では、自分とは違うタイプの子とも話す機会があり面白いと、高良さん。
 右:最近は『寺子屋だんだん』のイベントである年金や保険などの勉強会に参加しているという折原さん。
右:最近は『寺子屋だんだん』のイベントである年金や保険などの勉強会に参加しているという折原さん。
初日から18人ほどの来客があった「だんだんワンコインこども食堂」は、その後も0歳児から高校生まで40~50名が集まる場になっていきました。コロナ禍においては、食堂スタイルからお弁当のテイクアウトとなり、一堂に会することはできないものの、お弁当を渡す際に一人ひとりとコミュニケーションが取れるようになったことで、コロナ禍以前よりもつながりが濃くなっているようです。「食堂のときは子どもたちがグループでワイワイやっていたり、地域の高齢者の方が子どもたちと話をしながら食事されたりしていたので、あえて私たちが話しかけることはなかったんです。でも今は個別に声を掛けやすくなったので、家庭の状況や子どもたちのちょっとした心の状態がわかりやすくなりました」と、近藤さんはにこやかに話します。


■こども食堂の広がりと共に感じる違和感
2021年12月の調査では全国6,014カ所になったこども食堂ですが、取り組みが広がる一方で実際に利用する人と世間のイメージには温度差があると眞鍋さんは言います。自分が見ている「だんだん」と社会が見ているこども食堂にギャップを感じたのは3年前の高校3年生の頃。新聞やテレビの取材が増え、眞鍋さん自身も話を聞かれるようになったものの、「子どもの貧困」というキーワードと共に伝えられることに抵抗を感じたそうです。眞鍋さんは、子どもにとって普段体験できないことができる機会や場所だから「だんだん」に集まるのであり、生活に困っていて食事を安く食べに来ているわけではないという想いがありました。こども食堂の目的の一部である貧困対策や居場所づくりの背景には地域のつながりを大事にしたい想いがあるはずなのに、貧困対策と居場所づくりだけが目的のように伝えられることに違和感が出てくるというのです。ただ一方で、開始当初は子ども300円だった食事代を「ワンコイン(100円に限らずどんなコインでもOK)」とした背景には、どんな状況の人でも「だんだん」に来たら温かいご飯を食べて欲しいという近藤さんの想いもあります。
■「こども食堂じゃなくてもいいんだよ」
近藤さんのところにはメディアの報道を見てこども食堂を始めるための相談に来る人もいます。しかし、皆さん「こうしなければいけない」と思い込んでいるようで、こども食堂を開くのはハードルが高いと感じているようです。そこで近藤さんは「こども食堂じゃなくてもいいんですよ。人を想う気持ちが持てれば」と声を掛けています。数人の仲間でお茶を飲むだけでも、その地域の近況について話すだけでも、課題や魅力が見えたりするので、そういう機会を持てばいいのだと伝えています。
小学生の頃から「だんだん」に通う眞鍋さんは、地域の人とのつながりがあり居心地がいいから行くだけであり、「こども食堂」という名前を付けたから人が集まるわけではないと考えています。高良さんも、自分にとっては学校の教室が居場所であったけれど、公園が居場所の人もいるだろうから、誰かと安心して関われる場があればいいのではないかと言います。
 「だんだんワンコインこども食堂」のメインテーブルを囲んで。
「だんだんワンコインこども食堂」のメインテーブルを囲んで。
こうしたやりとりをしながら、近藤さんは目の前の若いボランティアたちが社会課題と正面から向き合っている姿に感心し、彼らの数年前に思いを巡らせます。「商店街でもいいし、なんでもいいんだけど、周りにどういう大人がいるかで変わってくるんじゃないかな。気軽に声をかけてくれる大人がたくさんいて、学べる環境があるのは良いことだと思います」
眞鍋さんは自身の体験を通して改めてこども食堂について考え始め、現在は大学で福祉を専攻し、こども食堂について卒業論文という形で向き合っていこうとしています。温かい地域のつながりの中で育った子どもたちは、地域に新たなタネを撒き始めるのかもしれません。